| 東亜医学協会会員店 |
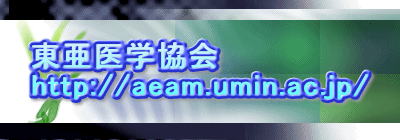 |
|
|
|
気血水というのは
目に見えない気は、働きだけあって形がありません。
気は血・水とともに体内を順行するエネルギーと考えれます。
息を吸うことによって天の気を、穀物を食することによって
地の気を体内に取り入れます。何らかの原因でめぐるべき気が
下の方に行かず、上方へ衝き上がってしまう。(気の上衝)顔ばかりほてって
手足が冷える状態です。
他に気の症状として、喉の付近に気が鬱滞する(気滞)、
気の不足(気虚)があります。
このように、東洋医学的には気の変調が血水の流れに影響していると
考えます。
体内を順行する血が何らかの原因で滞り、
病的症状を呈することをオ血といいます。
水は体内を順行しているといよりは、組織や器官での水分の偏在、
異常留滞が病的症状を作りだします。これを痰、痰飲または水毒といいます。
気血水のものさしに陰陽● 表裏●寒熱それぞれのものさしを
組み合わせ証を決めていくのですが、漢方では有史以来のきわめて長い経験則で
このものさしを患者さんの病態の上に置き、治療します。
ですから、一度完治すると再発することは、まれです。
|